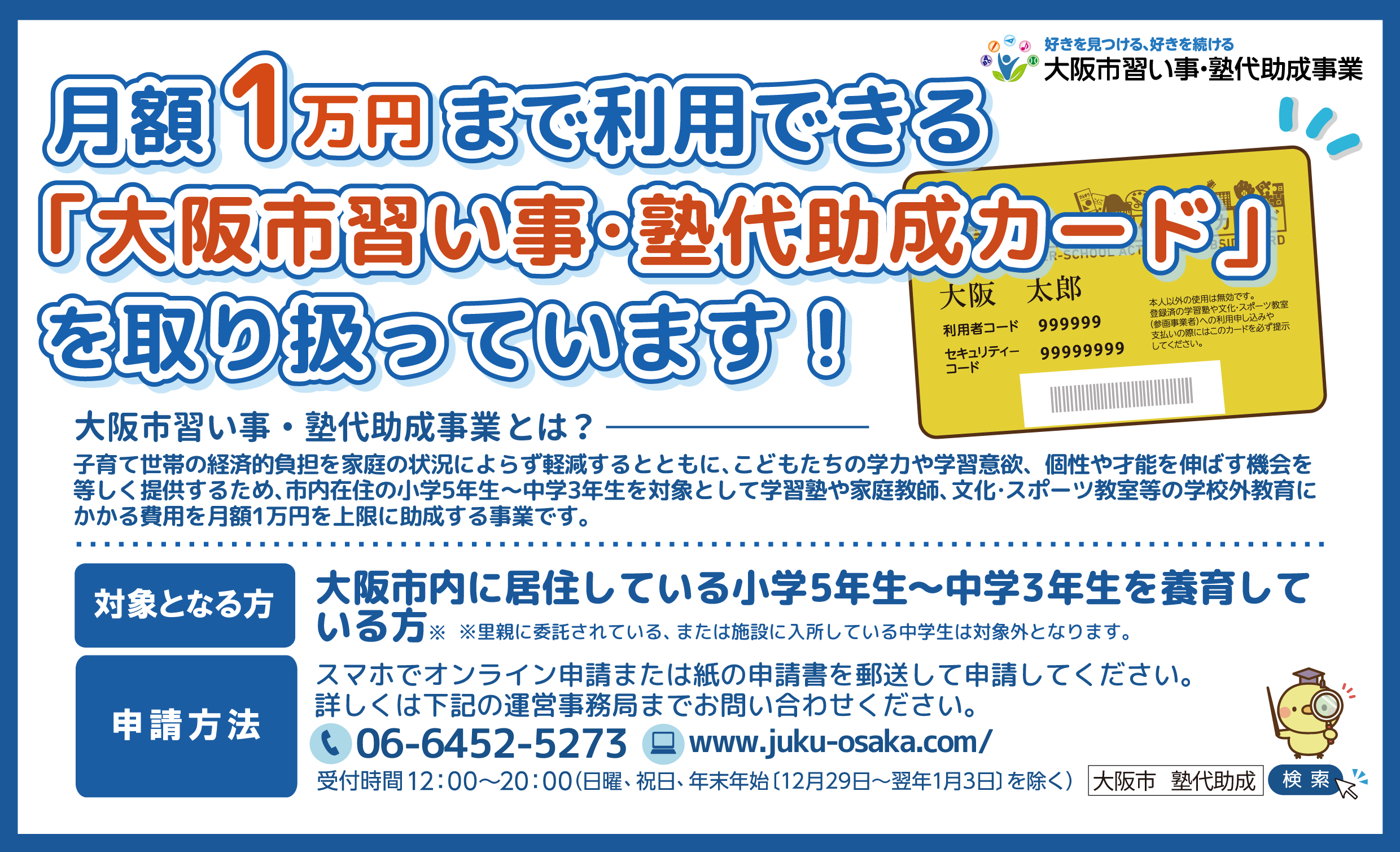数学を伸ばすために、大切なこと
進学塾・進学予備校Excia|塾長コラム
今日は数学の勉強方法について。
中学生の子にもわかりやすいように、語いのレベルを考えて書いていこうとおもいます。
数学を学ぶ上で、最も大切だと私が思うのは・・・
↓
↓
↓
↓
↓
↓
途中式
途中式をしっかり書いて計算処理しているか。
これで数学の力は大きく変わります。
(※頭の中の処理速度が速すぎて、書かない子もいます。
今回は高得点が取れているケースではなく、数学の得点が伸び悩んでいる生徒の例。)
実際、入塾した生徒のまず何を見るかといわれたら、
私は、その子がこれまで解いてきたワークやノートを見ます。
問題のページや日時を書いている?
字の大きさ、余白はどうだろう?
ノートやメモを書くとき、何を大事と感じ、何を必要ないと感じている?
暗算するタイプ?ノートの端に計算するタイプ?
書いた計算は消しゴムで消してしまう?残している?
などなど・・・
もっとたくさん、見ている点はありますが💦
ワークやノートは、その子のこれまでの勉強法を読み取れる情報の宝庫です。
そして一番重要なのが、先ほど挙げた途中式の有無。
数学って、与えられた情報をきちんと一つずつ処理していく科目。
その処理の過程が残っているか、またそれを見るだけでも、
その子の苦手や得意ってわかります。
数学を教えている方でしたら、共感してもらえる・・・はず。
いやいや、途中式なくってもええやん。答え合ってるし。
頭の中では「分かってる」。書かなくてもええやん!
ノートもったいないし…
と、思う子もいるかもしれませんね。
というか、こう思っていることが多いと感じます。
でも、書くことによって得られるメリットの方が、数学は圧倒的に多い。
書かないことが、結果として、数学の力がつかないことに結び付いています。
① 途中式を書かず、答えだけ
頭の中で「こうだな」と考えて答えを書いちゃう。
でもそれだと、あとでどこでつまずいたか分からないまま。
だから「惜しかった!」「計算ミス!」で終わらせてしまうことがほとんどです。
数学は考え方をたどる、そして一つずつ処理をすることによって上達する教科です。
だからこそ、途中式=あなたが考えた跡が残っているかってホントに大事。
指導する際、私たち講師も「どこでつまずいたか」を見ます。
途中式がないと、問題の解説はできるけど、あなたが本当に間違ったことについて的確な指導はできません。
いやいや、頭の中にあるからええやん!という子もいるでしょう…
でもそれってすぐ忘れるし、復習の時、確認すらできないよ・・・?
② 途中式の書き方がそもそも頭の中にすら無いことも
入塾したての生徒に、「途中式どう書くの?」と聞くと、「え、書く必要あるの?」って返ってくることがあります。
つまり、途中式自体の重要性をこれまで習っておらず、書く必要性すら認識できていない。
例えば「(−3)×(−5)ー8÷(-2)=」って問題で、「11」とだけ書いて終わり。しかも間違っている。
なんでこうなった?を残していない。
「なぜそういう計算になったの?」と聞くと、
「えっと…なんとなく…」
とか
「わかりません」
と答える子も…。
そのままでは間違いの原因もわからず、次も同じように迷ってしまいます。
教科書にあるような、途中式を書く。
型を真似てみる。
これはめんどくさくて遠回りに見えるかもしれません。
でも実は近道。
まずはうまくいくとされている方法を素直にまねることで
ぐっと伸びる子はあきらかに多いと感じます。
面倒くさがっちゃだめ。
数学は、面倒なことほど取り組めば力が付く科目。
そしてやればやるほど、上手くなっていく科目。
③ 赤ペンで解説を書いて終わりにしちゃう
「間違えたところに赤ペンでメモしました」ってノートもよくみます。
いいんです、書いたのは。提出もある場合は特にね。
だけどね、そこで終わると分かった気で終わっちゃいます。
答えが見えただけでは、理解にはなっていない…。
答えだけ書いて、わかった気になっている子は山ほど見てきました。
ただ、本当に理解してるなら、同じ問題をもう一回、自力で解けるはず。
というか、解ける。
できないなら、できるようになるためのことを考える。
そのためには解説を自分の言葉で書く・もう一回解き直すが大切なポイントです。
それがないと、また同じミスが出るし、わからないままです。
④ ノートがごちゃごちゃで振り返れない
保護者の方でも、
こどものノートを開いたら文字も式もぎゅうぎゅうで
「これ、どのページの、何の問題・・・?」
となっているノートを見たことありませんか?
それも数学が苦手な子の共通点です。
行にあわせて書けていない、字もナナメ…
そうなっていると危険信号。
ノートって、書くための紙じゃなくて、自分が考えを改めて見る場所です。
だから、1行空ける、見出しをつける、図解してみる。
ちょっとした整理が、計算のしやすさ、あとからの復習のしやすさを生みます。
ノートはただ雑につかうものではなく、上手く使うこと。
字のていねいさはあまり気にしません。(小さすぎて計算ミスがある場合は別)
きちんと「情報」が整理されているかが大切です。
⑤ 間違うのがイヤで書かない
途中式を書かない子には間違うのがイヤという気持ちが隠れていることもあります。
(これはほかの科目でもありますが💦)
書いたら〇つけの時に「これ間違ってる…」って恥ずかしくなってしまう。
だから最初から書かない。
でも、それでは成長できないんです。
書いて確かめることをすれば、失敗もチャンスになります。
「どこでつまずいたか」が見えるから、 その気づきが次の理解につながります。
何かを学ぶことは、間違いながら進むことです。
最初からすべてカンペキ!なんてことはありえません。
ではどうしたらいいの?
今日からでもできることを3つだけ。
- 授業ノートの冒頭に「今日の目標」を書く。 →「この単元をやったら、何ができるようになりたい?」を自分に問いかけて、目標をつくりましょう。
- 途中式・考え方・なぜこうしたかを、まずは教科書の真似をしてみましょう。
- よく間違えた範囲は復習ノートを作って振り返る。 →間違えた問題を書き直し、「なぜ間違えたか」「次どうするか」を書いておきましょう。
3つ一気にではなく、まずは2つ目までをしっかりやってみましょう。
慣れてきたら、自分の間違いの傾向が分析できるようになります。そこから3つ目にチャレンジ!
さいごに
数学が苦手な生徒のノートには、同じクセがひそんでいます。
でもそれは逆に言えば、そのクセを変えれば苦手から得意に変えられるということです。
Exciaでは、書く力も考える力も、一緒に育てています。どの生徒もノートの書き方から指導するくらいです。
もし保護者の方で「うちの子のノート、なんか…」と感じたら、 どうぞ一度ご相談ください。
ノートの使い方を変えることが、数学を変える第一歩です。