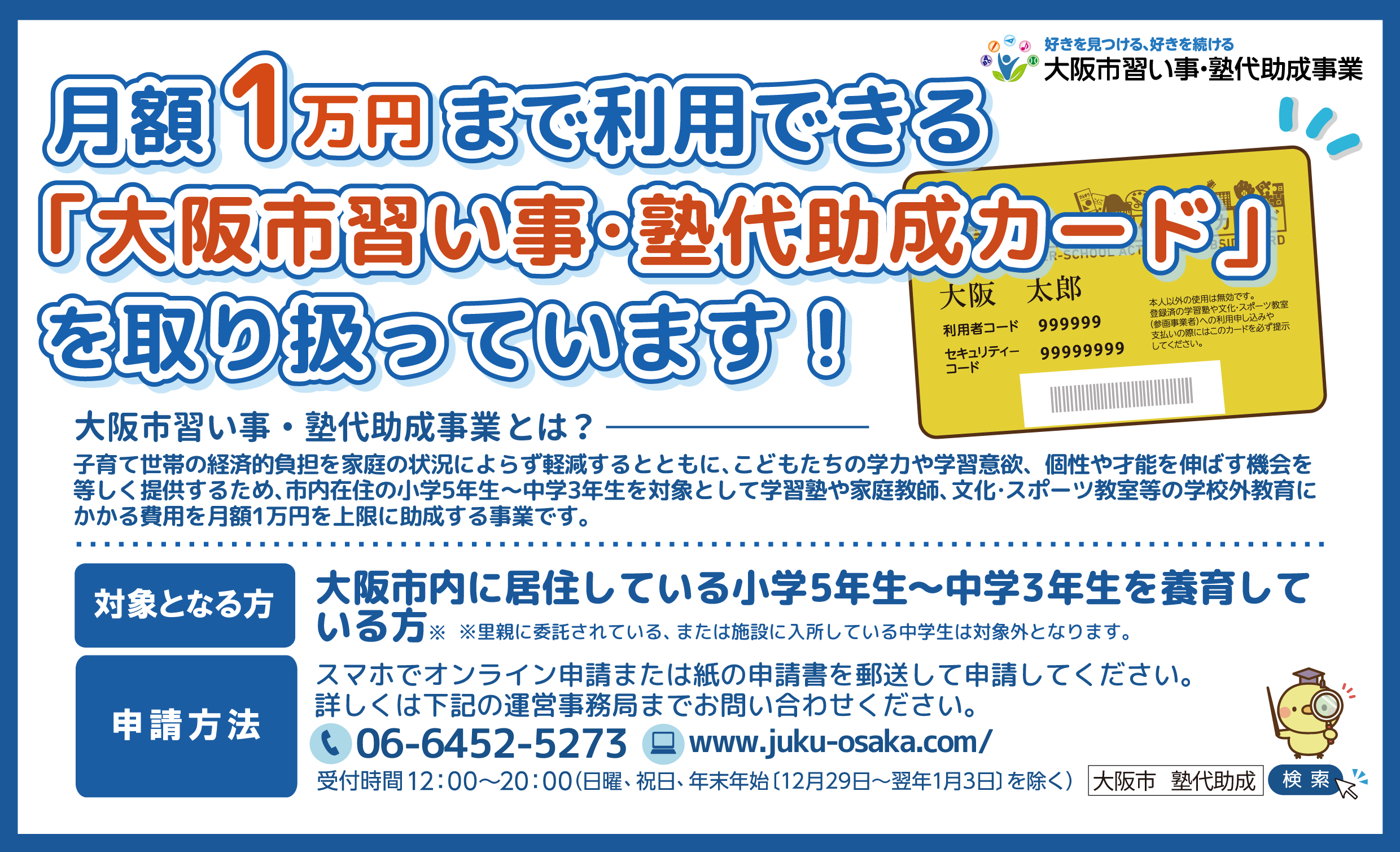2025年度 関西私大 “最終志願者数の前年比” を、見てみよう
関関同立/産近甲龍/摂神追桃の12大学を、伸び率でズバッと横並び
9月。ここから“全員が本気”になります。
もう9月の半ばなのに、今日も暑いですね……
教室のクーラーは今日もフル稼働。今週末に雨が降って、そのあとは涼しくなるそうですがほんまやろか…
さて、ここからは受験のお話し。
もう9月。受験生はほんとうに空気をかえないといけません。教室もピリッ、私も例年のごとくエンジン全開です。
ここからは全員が本気で取り組まないと合格はいとも簡単に逃げていきます。
で、勉強量を増やすのは当たり前として、同じくらい大事なのが出願の設計です。
どこを受ける? 何方式で? どの日程で?
これを緻密に計画することこそが、そのまま合格率に直結していきます。
やみくもに受けるのではなく、戦略的に。受験校・学部・日程選びは安易に選ばない!
今月〜来月頭の優先順位って?(順番が大事)
- 出願の設計:受ける大学・方式(独自/共テ)・日程(前半/中盤/後半)をまず決め切りましょう。
- 得点の見える化:過去問は必ず解く!各科目の取り切りライン(合格最低点)との差を数値で把握しよう。
- “混み具合”の把握:同じ実力でも、出願が集中した大学・方式は合格点が上がりがち。だから人気の変遷(前年比)を先に押さえよう。
- 志願者の“増減”だけ見て、実受験者数や合格者数を見ない(=実質倍率が読めない)。
- 受験校の日程が密集していて、本命に向けた場数が足りない(=実力を出す機会が少ない)。
- 独自方式と共テ利用の出し方のクセを調べず、“なんとなく”で出願してしまう。関関同立に共テ利用本筋・・・なんて言わないよね?
資料(前年比グラフ)について
- 中央が±0%です。右(青)は“増”、左(赤)は“減”。混み具合の目安として使います。
- これを読んでいるあなたの併願リストに重ねて、増の大学=方式を分散、減の大学=狙い目方式がないか探してみよう。
ということで今回は、最終志願者数(一般選抜:2月)の前年比で、関西の主要12大学の増減をリストにしました。
数字は「去年はどこに人が集まったか」くらいにとらえましょう。
前年比ランキング(12大学|一般選抜の最終志願者ベース)
※横並び比較のため、私立の一般選抜(主に2月)に絞った“最終志願者数の前年比”で見ています。バーは中央が±0%。右へ行くほど増、左へ行くほど減です。
関関同立=関西・関西学院・同志社・立命館/産近甲龍=京都産業・近畿・甲南・龍谷/摂神追桃=摂南・神戸学院・追手門・桃山。数値は各社公開資料を横並び化した要約(一般選抜の“最終志願者数”の前年比)。
数字の読み方——“人気=難化”とは限らない理由
「志願者が増えた=むずかしくなる」は半分正解、半分ちがいます。本当に効くのは実質倍率(受験者÷合格者)。同じ“増”でも、合格者を広く出す大学と、きゅっと絞る大学で体感難度は変わります。
- 方式のクセ:独自方式は絞り気味、共通テスト利用は広めに出す年がある。大学ごとのクセは毎年チェック。
- 併願割・定額制:出願しやすくなり“見かけの増”が乗る年も。実受験者で見直すクセをつけましょう。
- 学部の波:情報系・法・経済経営商など、時流で伸びる学部がある。大学合計の数字だけで判断しない。最近だと経営学部の女性比率が増えています。
出願戦略にどう落とす?——塾長の鉄板ステップ
- 志望群を3段に分ける:挑戦/実戦(合格可能性50〜70%)/安全。各群で大学×方式×日程を最低2つずつ確保しよう。
- 過去問の“取り切りライン”を見える化:配点に沿って得点表を作り、合格最低点との差を数値できちんと把握しよう。
- 日程をずらして“場数”を確保:前半で当てる・中盤で固める・終盤で拾う。甲南のように日程の工夫が効く例は毎年あります。
- 方式のミックス:独自方式+共通テスト利用で網を広げる。科目相性で勝てる方式を優先しましょう。
さいごに
9月からの受験は、「情報×設計×実行」の三拍子。数字は出そろいました。
あとは、あなたの得点力が一番届くルートを一緒に引くだけ。
迷ったら、いつでも教室で相談してくださいね。いつでも真剣に、あなたをサポートします。